※当ページのリンクには広告が含まれています。
ご覧いただきありがとうございます。
今回ご紹介する一冊は小川哲さんの
「火星の女王」です。
本作は、NHKが放送100年という節目に、”これからの100年を考える”という 「宇宙・未来プロジェクト」 の中で生まれた物語です。
2025年12月13日(土)から3週連続でドラマとして映像化されています。本書はその原作となる作品です。
※見逃した方も『NHKプラス』のアプリを取れば見れます。
舞台は人類が火星に移住して40年が経過した未来となっています。
ジャンルとしてはSFでありながら、物語には“ミステリー要素”や“人間ドラマ”も織り込まれています。
この記事では、できる限り具体的なネタバレを避けつつ、その魅力を解説していきます。
皆様の読むきっかけになれば嬉しく思います。
あらすじ・概要
| 発売日 | 定価 | 出版社 | ページ数 |
| 2025/10/22 | 1650円 | 早川書房 | 320P |
『スピラミンという物質の結晶構造の変化を発見』
この発見によって地球と火星の人々の心は交錯していきます。
発見したのは火星にやってきた生物学者であるリキ・カワナベ。
一方で火星で生まれ育った人間の存在もいます。リリーE1102は地球観光に行くことを夢みる学生。彼女は遠心型人工重力施設に通い、地球に降り立つ日に向けて準備を整えています。
そして、地球の白石アオトはこの物語の重要な組織となるISDAの職員として、リリとの約束を果たす日を待ち望んでいます。
しかし、スピラミンに関する発見が、2つの惑星を揺るがし、思わぬ出来事をもたらしていきます。
本書の魅力を解説
ここからは本書の魅力を深掘りして、
紹介いたします。
SF初心者にもおすすめ!ストレートなSF作品
SFというジャンルに馴染みがない方でも、すんなり物語に入り込める一冊だと思います。
小川哲さんの作品には、「そんな視点!?」と驚かされる独特の着眼点が詰まっています。その驚きが癖になる作品が多く、まさに小川哲さんならではの魅力だと思っています。
そして、ジャンルも多彩で、SF作品も手掛けてきた作家さんです。
そんな中、本書は“ストレートなSF”に位置づけられる一作ではないかと感じました。普段SFを読まない方であっても、SFの世界を堪能できる作品だと思います。
私自身も普段からSFを読むわけではないのですが、むしろ他のSF作品を読みたくなりました。皆さんも新しいジャンルの扉を開くきっかけになるかもしれません。
著者の独特な魅力が絶妙な濃度で調整されていて、SFを普段読まない方でも楽しめる一冊に仕上がっていると感じました。本作は、著者の過去のSF作品へとつながる”入り口”にもなる作品だと思いました。
小川哲が描く100年後の世界と人間の本質
100年後の未来は想像を絶するような世界。そう思う方も多いのではないでしょうか。
今の時代ですら、AIが日進月歩で進化し、変化のスピードについていくのがやっとです。
ところが、この作品のおもしろさは未来が『今とそれほど変わらない』というところにあると思います。
もちろん、舞台が火星というだけで大きな違いがありますし、100年という時間の中で技術が発展しているのは間違いありません。
それでも根本的なところは、現代とほとんど変わらないと感じさせられます。今の時代を基準に具体的に想像しやすいというのが、この作品の読みやすさにも繋がります。
そして、最も進化していないのは、人間だと感じました。
100年経ったとして、人間が持っている“欲望”や“野心”は今と変わりがありません。
それを皮肉っているようにも感じますし、それが人間の本質なんだと捉えているようにも感じます。
SF作品でありながら、人間とは何かを頭の片隅で考えさせられるという感覚が、とにかくおもしろいのです。
地球と火星で交錯する人間ドラマ
そんなふうに、どこか風刺的な視点も感じさせる本作の魅力は、地球と火星で交錯する人間ドラマです。
驚くべきなのは、100年経ってもAIがすべてを支配している世界ではないということです。
もちろん、要所要所で“未来の姿”が描かれています。ところが、人間味がある物語でもあるのです。
“欲望”や”野心”が渦巻いているのも事実ですが、それだけではありません。
おそらく、欲だけで突き進めば、人間は簡単にAIに支配されてしまうんだと思います。そんな未来には、きっと“人間ドラマ”は存在しないはずです。
だからこそ、この物語の結末はこうだったんだなと思いました。小川哲さんは未来の世界を描きながら、今を生きる私たちに思いを馳せたのだろうと、様々に想像したくなる展開でした。
本書の感想
未来を描いた作品には、想像以上の何かを求めてしまいます。
ところが、『これだけ技術が進んでいるのに、まだこうなんだ』という、どこかちぐはぐな感じの描写がおもしろいのです。これがまさに進化のリアルだなと思いました。
例えば、インターネットが家庭に普及し始めた頃を思い出します。
インターネットにより世界と繋がるようになり、WEBゲームにはまった時期があったんです。
遠く離れたユーザーと交流しながらゲームを楽しむことに、すごく感激したことを覚えています。
ところが電話回線を使っていたので、電話かネットのどちらかしか使えない状態だったと思います。そして、今と比較すれば、WEBページの表示はとてつもなくタイムラグがありました。
進化すれば、そこにはまた不便な問題が生まれます。物語の中でも、通信の面などで同じようなことが描かれているなと感じました。
だからこそ、100年はかなり先のように思えて、近い未来なんだとも感じます。そんな絶妙な距離感もこの作品にはあるんだなと感じました。
ぜひ、100年後の世界を本書で体験してみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
小川哲さんの『火星の女王』はこちらからどうぞ。
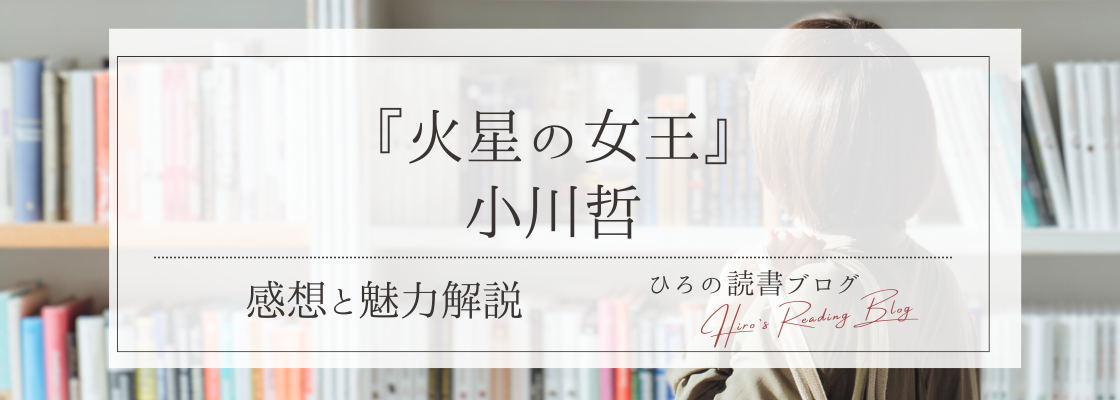
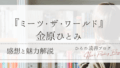
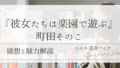
コメント