※当ページのリンクには広告が含まれています。
ご覧いただきありがとうございます。
今回ご紹介する一冊は夏川草介さんの
「エピクロスの処方箋」です。
本作は2023年に刊行された『スピノザの診察室』のシリーズ続編となります。
注釈として、”シリーズではありますが、本作単体としてお楽しみいただけます”とされています。しかし、本記事では前作との関係も併せて魅力を解説していきます。
なぜなら、「今作だけ」で楽しむよりも、前作があるとより楽しめる作品だと考えているためです。
その理由も非常に重要だと思っていますので、できる限り具体的なネタバレを避けつつ、本書の魅力をお伝えしたいと思います。
この記事が、皆様の読むきっかけになれば嬉しく思います。
あらすじ・概要
| 発売日 | 定価 | 出版社 | ページ数 |
| 2025/9/29 | 1980円 | 水鈴社 | 360P |
大学病院の准教授である花垣から、難しい症例が持ち込まれました。
母を亡くした甥との生活のため、地域病院で内科医として働く雄町哲郎。大学病院とはかつて勤務していた病院であり、花垣は先輩医師です。二人はこれまで数々の難手術を成功させ、お互いの力量を認め合う二人。
その過去については、前作の時点では詳細は語られていません。
今回の難しい症例の患者は82歳の高齢男性。そして、かつて病院を去る哲郎に対して激怒した大学病院の絶対権力者・飛良泉寅彦教授の父親でした。
大学病院時代の過去にも触れながら、前作を越える”温かく、熱い”物語がここにあります。
そして、快楽主義を提唱した古代ギリシャの哲学者『エピクロス』が主張するのは快楽の本質。
タイトルにもなったエピクロスの哲学にも触れながら、再び雄町哲郎が患者の心を救っていくのです。
本書の魅力を解説
ここからは本書の魅力を深掘りして、
紹介いたします。
『エピクロスの処方箋』が描く”医療の無力感”
この作品の最も印象的な点は、医療小説でありながら“無力感”を感じるところです。
ただし、この無力感は決して絶望ではありません。むしろ、作品全体に柔らかさと温かみを与える役割を担っています。この作品の不思議な魅力なんですよね。
雄町哲郎をはじめ、花垣や同僚医師たちは皆、確かな技術と知識を持つ優秀な医師です。それでもなお、医療の力では届かない“壁”が立ちはだかるのです。
この正体を紐解いていかない限り、この物語の奥深いところにある『芯の部分』にはたどり着けません。その芯の部分にこそ、静かでありながら確かな情熱があるのです。
この感覚は前作『スピノザの診察室』から続くもので、今作ではその部分を紐解くように、深く繊細に語られていくのです。
今作から読む方でも十分楽しめますが、作品の根底にあるテーマをより深く理解したい方は、前作を先に読むことをおすすめします。
雄町哲郎の哲学とは?『生と死』を考える医師の物語
雄町哲郎は『生』と『死』に哲学を持った医師です。
本作では物語の根底にあるテーマが紐解かれることにより、雄町哲郎がどういった医師なのかが分かっていきます。
彼を「優れた技術と豊富な知識を持つ医師」として語るだけでは、到底物足りないのです。
花垣をはじめ、同僚医師たちから慕われる理由も、ただ「人が良いから」ではないのです。
特に印象的なのは、大学病院から研修に来ている南茉莉(みなみ まり)との関わりです。
かつて大学病院で働いていた雄町は、地域医療の現場に身を置くことで、「医師としてのもう一つの在り方」を見出した人物。
単に優しいとか患者に寄り添うともまた違う彼の姿は、同じ医師である南には別次元の存在なのではないかと思います。
それこそ、根底にある『生と死の考え方』そのものが違うのです。
そこには、哲学が存在するのです。科学だけで立ち向かえない『生と死』に哲学を持って対峙する雄町哲郎の姿が読者を惹きつけます。だからこそ、このシリーズには哲学者の名前が入るんですね。
さらに今作では、大学病院時代の絶対権力者・飛良泉教授との再会を通して、“雄町の医師としての哲学”と“病院の特殊な権力構造”が衝突します。
この対立こそ、本作をより深くする最大の見どころです。
あたたかさと熱が織りなす物語
京都を舞台とした小説は、それだけで魅了されるような雰囲気があります。
ただ、その空気感をより濃く感じられるのは、前作の方かもしれません。たとえ、医療の緊迫するシーンがあっても、この作品にはいつも、あたたかく心地いい風が吹いているのです。
今作では、雄町自身や心情描写に、より多くの時間と言葉が割かれています。この物語にあたたかさだけではない、“熱”を注いだのだと感じました。
読者としてはシリーズの続編には、大きな期待が膨らみます。それと同時に、「失望したくない」という気持ちもあると思います。人間は心理的にも失敗を避けたい生き物ですから。そのため、「続編を読む」という行為自体が、小さなチャレンジとも言えます。
ところが、この作品はあたたかさと熱のバランスを絶妙に変えたことで、その期待に真正面から応えてくれたような素晴らしい1冊でした。
これは、「このシリーズが気になる方」も「続編を読むか迷っている方」にも、背中を強く押す理由の一つとなりました。
本書の感想
「医療小説は面白いなぁ」と、単純に思いました。しかし、物語は生と死に深く関わるものです。
では、なぜ医療小説は面白いと感じるのでしょうか。
それは、おそらく病を乗り越え、未来に向かって元気に生きる人の姿を思い浮かべるからかもしれません。
こうした出来事は”奇跡”と呼べるものであり、起こる確率が低いことが上手くいったことによる感動なのかもしれません。その感動は、読者にも希望を与えます。
ところが、本書で思い浮かべる奇跡は違うのです。日々生きていること自体が、そもそも奇跡なんです。誰にでも訪れる「最期の瞬間」を、心穏やかに受け止めるための奇跡の連続なんです。
その上で、雄町哲郎は医師として、他人の人生にどう関わるかということを誰よりも深く考えたのだと思います。
「おもしろいな」というのは、まさに雄町哲郎の思考に共感するものがあったからです。希望の光というよりも、静かで決意のこもった熱量に心を動かされたからだと思います。
この静かな情熱をまた感じたいと思います。そして、雄町哲郎の意思や哲学を受け継ぐ者が、今後現れてくるんだと確信しています。だからこそ、次回作があることを心から願っています。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
夏川草介さん『エピクロスの処方箋』はこちらからどうぞ。
■前作の『スピノザの診察室』もぜひ読んでみてください。
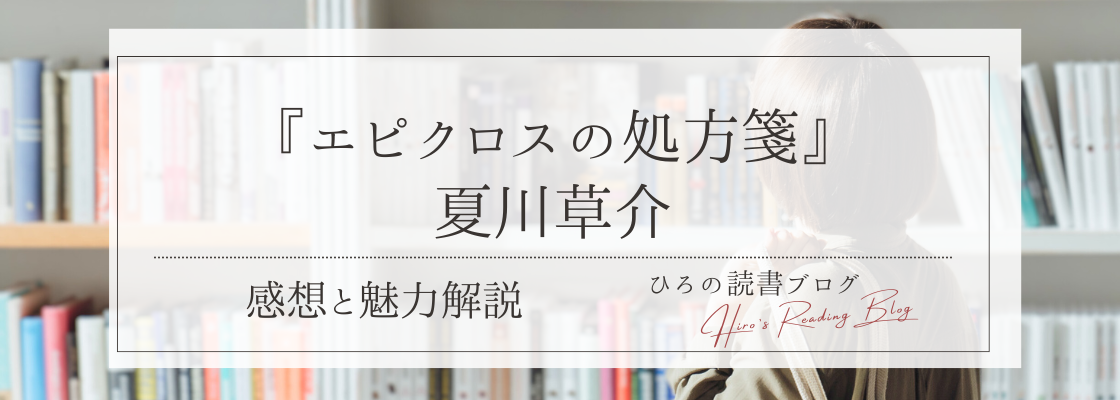
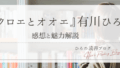
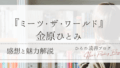
コメント