※当ページのリンクには広告が含まれています。
ご覧いただきありがとうございます。
今回ご紹介する一冊は山口未桜さんの
「白魔の檻」です。
前作『禁忌の子』が話題となり、2025年本屋大賞にもノミネートされました。
現役医師でありながら作家でもある著者の注目度は高く、書店では一時在庫切れになるほどの人気でした。
そんな著者による待望の2作目が誕生。しかも、シリーズ第2弾ということで、待ち望んでいた方も多いのではないでしょうか。私もその一人として本書を手に取りました。
できる限り具体的なネタバレは避けながら、本書の魅力や感想をお伝えしていきます。ぜひ、参考にしていただければ嬉しいです。
あらすじ・概要
| 発売日 | 定価 | 出版社 |
| 2025/8/29 | 1980円 | 東京創元社 |
| ページ数 | 備考 | |
| 335P | 『禁忌の子』に連なる、 シリーズ第2弾 | |
今作から読んでも楽しめるか?
結論から言うと、前作を読んでいなくても問題なく楽しめます。
今作はシリーズ第2作目にあたりますが、物語としては独立しており、完全な続編と考える必要はないかと思います。
前作で登場した人物のひとりが引き続き登場しますが、物語の理解に支障はなく、今作から入っても十分に世界観を味わえる構成になっています。
あらすじ
研修医の春田とともに、北海道に派遣されることとなった城崎。この”城崎”が前作にも登場し、大活躍した医師なのです。
そんな二人が向かったのは、温泉湖の近くにある山奥の病院。
つまりは、「過疎地の医療現場」なのです。
二人が辿り着い直後に、その病院は閉ざされることに…。過疎地の病院が完全に孤立するという舞台が整います。
閉ざされる原因となったのは病院一体を覆う濃霧。そして、誰も出入りのできない空間に病院スタッフが変死体となって発見されるのです。
翌朝に大地震が起き、病院の周囲には硫化水素ガスが流れ込む。霧とガスにより孤立した病院で不可能犯罪が発生し、事態は一気に絶望へと向かいます。
物語はその絶望を味わいながらも、医師たちの奮闘、次第に明らかになる“犯行に至った真実”。
ラストを迎えた瞬間に突き付けられるものとは…。
本書の魅力を解説
ここからは本書の魅力を深掘りして、
紹介いたします。
クローズドサークルと化した医療現場
前作の『禁忌の子』が「冒頭からの衝撃」で読者を掴んだとすれば、今作の『白魔の檻』は「じわじわと迫りくる静かな絶望」で読者を引き込みます。
さぁ今回はどんな展開が待っているのだろうかと、前作を読んだ人なら、あの余韻が再び蘇るような期待感が膨らむ序盤です。一方で、今作から読み始める方もすぐに物語の背景や舞台設定が掴め、“閉ざされた病院で起きる異常事態”というミステリらしい世界観に引き込まれるでしょう。
あらすじの時点で「クローズドサークル」であることを提示し、普段あまりミステリを読まない方にとっても、王道の設定として楽しめるかと思います。
※クローズドサークル:外部との行き来や連絡が不可能な閉ざされた状況
ところが、病院という特殊な構造と医療現場特有の緊張感を組み合わせることで、前作よりも設定が複雑化し、ミステリとしての厚みも増しています。
それでいて、破綻せずに進んでいく展開と城崎先生の冷静かつ客観的・論理的な推理が全体を引き締めてくれます。ミステリというジャンルを選んだ以上、土台の設定に関しては妥協を許さないという覚悟のようなものも感じました。
制約のある舞台で描かれる極限の絶望。その先に待つ展開は、ミステリファンだけでなく、医療ドラマやサスペンス好きの読者にも存分に楽しめる一冊です。
現役医師だからこそ描ける緊迫の現場
現役医師である著者は、医療現場の描写で本領を発揮しています。医療の知識を知っているだけでなく、それを文字だけで読者に伝える難しさまで理解している。そんな手腕が随所に光っているのです。
特に印象的だったのは二つの緊迫シーンです。
一つ目はカルテを扱う場面。詳細は語れませんが、読んでいるだけで鼓動が早くなるようなリアルさがあります。カルテは客観的事実しか書かれないため、着色せずにその緊迫感を伝えるのは極めて難しいはずです。それを、著者は見事に表現しています。
医療や介護など、人の命を預かる現場では、客観的な事実だけで構成された記録でも、熟練した者であれば、その文字から緊迫感を読み取ることができるものです。
二つ目は実際の現場での救命シーン。医療ドラマで想像できるような状況ではありますが、この場面には二重の緊迫感があります。ひとつは、救命そのものの極限状況。もうひとつは、同じ空間に犯人が潜んでいる可能性があるという心理的緊張です。
病院という閉ざされた特殊な空間では、この矛盾が読者へ気の許せない心理状態を生み、どこかに綻びが出ないか目を光らせたくなるシーンです。
2種類の緊迫感を綻びなく表現する緻密さも、現役医師である山口未桜さんの真髄を見せつけられた場面でした。
ぜひ、読む際にはこの二つのシーンにも注目してみてください。
ミステリの結末が突きつける医療の現実
山口未桜さんの作品は、「ミステリを書くために医療現場を生かした」というよりも、むしろその逆だと感じます。医療が抱える課題や現場のリアルを伝えたいからこそ、命の現場と相性の良いミステリというジャンルを選んだのではないでしょうか。
ミステリの謎が解けた時、見えてくるものは“医療の課題”です。私たち素人には到底立ち向かえない問題であっても、その影響は私たちの生活に少なからず及ぶ可能性があります。
そして、著者はその課題に自分なりの形で向き合い、物語に反映しているのだと思います。私たちが外から見るだけでは分からない、現場特有の感触がそこにはあります。
物語が結末に向かっていくに従って、物語は新たな表情を浮かべるのです。ミステリの高揚感とともに、その深刻さを突きつけるクライマックスは印象的でした。
2作品目にして、よりこのスタイルが浮き彫りとなり、著者の作風を理解する機会にもなりました。
本書の感想
本作から読んでも十分に楽しめますが、個人的にはぜひ前作も読んでほしいと思います。
まだ著者の作品は2作目ですが、だからこそこの2作を通して読むことで、山口未桜さんという作家の核が見えてくるはずです。
そして、その2作品が次の作品への期待へとなり、私たちの読書ライフの楽しみを一つ増やしてくれます。
もちろん、それだけではありません。この物語に登場する城崎医師の理解にも繋がります。登場人物の中でも群を抜いて魅力的かつ謎めいた存在と言えます。
2作品を通して読んでもなお、「この人物のすべてはまだ見えていない」と感じさせる奥行きがあるのです。
まだまだ、秘めたものがあると感じる山口未桜さんに、これからも期待が膨らむばかりです。
ぜひ、前作『禁忌の子』とあわせて読んでみてください。きっと追いかけたくなる作家さんの一人になるのではないかと思います。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
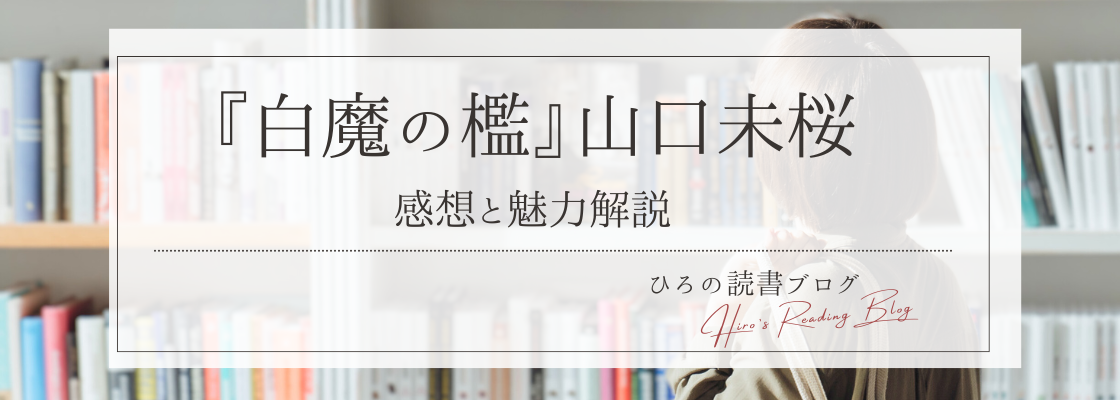
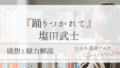
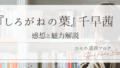
コメント