※当ページのリンクには広告が含まれています。
ご覧いただきありがとうございます。
今回ご紹介する一冊は千早茜さんの
「しろがねの葉」です。
これまでに二度直木賞候補となり、2023年・第168回でついに受賞を果たした作品です。
美しく緻密な言葉選び、多彩な情景描写、そして人物の微細な内面まで巧みに感じ取らせる表現力。こうした魅力が、千早茜さんの人気を支えています。
今回の『しろがねの葉』は、千早茜さんが初めて挑んだ時代小説であり、その評価の高さから多くの人が著者を知るきっかけとなりました。
この記事も皆様の読むきっかけになれば嬉しく思います。できる限り具体的なネタバレを避けつつ、本書の魅力をお伝えしたいと思います。
あらすじ・概要
| 発売日 | 定価 | 出版社 | ページ数 |
| 2022/9/29 | 1870円 | 新潮社 | 320P |
舞台は戦国末期、シルバーラッシュに沸く石見銀山。
少女ウメは両親と生き別れ、稀代の天才山師である喜兵衛に拾われます。
そんなウメは、石見銀山の坑道で働き始めるのですが、そこに女の居場所がないことを痛いほどに感じさせられるのです。喜兵衛を慕い、坑道で働く男たちに憧れ、競い合うように育った隼人を羨む日々。
しかし、銀山の過酷な環境や銀堀りに課せられるものは重く、やがて男たちは躰を蝕んでゆくのです。
銀山で生きる者の宿命や苦悩を目の当たりにし、愛する人を何度失っても生き抜くウメの生涯が描かれた物語です。
本書の魅力を解説
ここからは本書の魅力を深掘りして、
紹介いたします。
性別の枠に囚われない、少女ウメの強さ
時代背景や銀掘りという力仕事の過酷さを考えれば、女性の居場所がほとんどなかったであろうことは容易に想像できます。
しかし、少女ウメは性別の枠に囚われず、銀山に足を踏み入れる女性としての道を切り開きます。
性別という縛りや足枷のような制約を必死に振り払うその姿に、力強さとともに歯がゆさを感じます。
窮屈さを背負いながら、それでも男たちとは違った力強さが一つ一つの文章から滲み出てくるのです。
そんなウメにやがて“変化”が見られます。その変化は、ウメにとってはこの世界が作り出した残酷な運命のようにも感じました。しかし、それもまたウメの強さに繋がっていきます。
千早茜さんは女性を描くことに長けていると言われるのですが、本書が初読みであっても十分実感できると思います。一人の女性の生涯が、物語序盤から力強く描かれているのです。
五感に訴えかける文章力
歴史的背景のある物語となると、少し身構えてしまう方もいるかもしれません。
けれど、読み始めてみると驚くほど自然に、その時代や風景が頭の中に描かれていくのです。
きっと著者は、膨大な資料を読み込んだはずです。それでいて、その重さを感じさせずに物語の舞台へ自然に導いてくれるのです。
「これは読めそう」という安堵感を越え、「おもしろい読書時間になるな」と確信させる力が、文章に宿っているかのようでした。
そして、情景描写や登場人物の心情を緻密で美しく表現する力により、読むほどに気持ちは高揚していきます。
たとえば、鉱山の堀り口である”間歩(まぶ)”の暗闇を描く場面があります。その暗闇は単なる「黒」ではなく、底知れぬ恐れや、銀を掘る男たちが惹かれながらも飲み込まれていくような魔性を孕んでいるのです。まるで“黒より黒い闇”が目の前にあるかのような感覚に陥るのです。
山の独特な匂いがしてきたかと思えば、男たちが働き出す合図が鳴り響く。むせ返るような空気の重さ、蝕まれた身体の悲痛な声、そしてそれでも生きようとする生命の鼓動までが伝わってくる。
そんな五感すべてに訴えかけるような文章力が、この作品を一段と深い次元へと導いています。
描かれる圧倒的な生きる力
過酷な労働や銀に魅せられた男たちの姿。その中で、とりわけウメの力強さに圧倒されます。
肉体の逞しさではなく、「生き抜く力」の強さを感じさせられます。男たちを魅了する銀山を背景に、一人の女性の力強さや生命力を圧倒的に描いた作品だと感じました。
銀山は危険を伴う過酷な労働の場。それでも男たちは、間歩の暗闇に魅せられるように立ち向かっていきます。
それは「生きるため」という言葉だけでは語り尽くせない姿です。過酷さと背中合わせの官能、そして人間の本能的な衝動が、彼らを突き動かしているようでした。
『一体、銀山とはどういった存在なのか…』と、自然と考えずにはいられません。
愛する人を何度失っても、生き抜くウメの姿は、まるで銀山と重なるのです。
銀も命もいつかは尽きるものです。それでも、まるで尽きることのないような「生の光」がウメにはあるように感じます。そして、暗闇に挑んできた男たちは、その光を本能のままに求めたのかもしれません。
そういった対比や重なりを自分なりに考えてみることで、この作品の本当の魅力が見えてくるように感じました。ぜひ、様々に思いを巡らせてみてください。
本書の感想
本書の感想としてまず感じたのは、やはり作品の世界へ自然と入り込めることでした。
一見、読むハードルが高そうに思えても、それをすぐに覆すほどの文章力と構成力があるという証拠なのだと思います。本当に、魅力に満ちた作家さんだと感じます。
また、主人公のウメだけでなく、どの人物にも魅力や力強く生きる姿が描かれます。
読み進めるごとに『この物語は何を語っているのだろうか』と、もっと知りたくなるのです。
それは読み終わった後に余韻として残りました。この記事を書いている時でさえ、ふと手を止めて思いを巡らせるのです。そして、銀が眠る山を何度も想像しています。
やはり、この作品には大きな力が宿されているのです。そんな物語に出会えた喜びを、ぜひあなたにも実感してほしいと思います。
千早茜さんの『しろがねの葉』はこちらからどうぞ。
■単行本はこちら
■文庫版はこちら
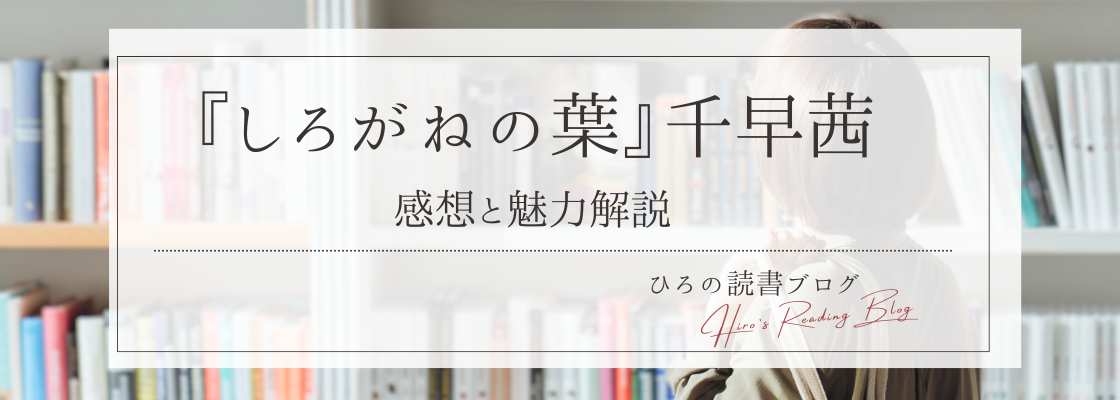
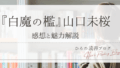
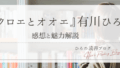
コメント